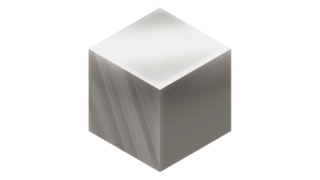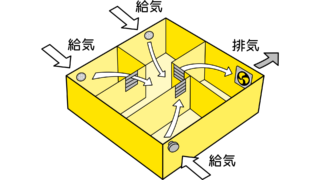突然の地震や停電、大雨など、災害はいつ起こるかわかりません。
「備えが大事」とは分かっていても、実際にどれくらいの量を、どんな物を用意すればいいのか迷う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、4人家族のわが家が実際に準備している防災用品と備蓄をリアルに紹介します。
「実際の家庭サイズで考えると、こんな風に用意すればいいんだ」とイメージしていただければ幸いです。
わが家やの家族構成と避難スタイル
まず最初にお伝えしなければならないのが、わが家4人の家族構成と家の立地条件などです。家族構成や立地によって避難の方法が変わってくるので、自分にはどのスタイルが合っているのかを考えることが大切です。
災害時における避難行動は、内閣府・消防庁によると大きく分けて4種類あるとされています。
①在宅避難
自宅が安全でライフラインや建物の損傷が軽い場合、自宅で避難生活を送るスタイル。
②避難所への移動避難
学校・公民館・体育館など自治体が指定する避難所に移動して生活するスタイル。ハザードマップの危険域に該当する地域に住んでいる方はこの避難が推奨されます。
③親戚・友人宅への移動避難
指定避難所以外の安全な地域にある知人・親族の家に身を寄せる。不特定多数が集まる避難所ではプライバシーが気になるという方はこちらの避難方法が適しています。
④車中避難
駐車場や安全な場所に停めた車内で過ごすスタイル。プライバシー空間の確保ができる一方で、エコノミークラス症候群などの健康リスクに注意が必要です。
私の家の避難スタイルは・・・
私の家族は大人2人・子ども2人の4人家族でペットはいません。家は戸建てで今のところ家族に大きな病気やケガはありません。また、家の位置はハザードマップの危険域に該当していないので、在宅避難を前提とした備えをしています。
避難の方法によって持つべき物の種類や在庫数が変わってくるので、その点も含めて見てただければと思います。
行政が推奨する備蓄の目安
内閣府や消防庁のガイドラインでは、「最低3日分」の備蓄が推奨されています。ただし、近年の大規模災害を踏まえて「できれば1週間分以上」の備蓄が望ましいとされています。
たとえば水においては、1人1日あたり水3リットルを目安に準備することが推奨されています。
| 1人1日分 | 4人×3日分 | 4人×7日分 |
|---|---|---|
| 3L | 36L | 84L |
わが家では、子どもがいることも考慮して「1週間以上耐えられる設計」を目指して備えを整えました。
わが家が実際に置いている防災備品
防災備品の種類や用途はさまざまです。それぞれのカテゴリーごとに、わが家で実際に置いているアイテムを紹介していきます。
電気・照明・情報収集
- 充電式ランタン ×2
- 充電式ライト ×4
- 手回しライト ×1
- 充電式ラジオ ×1 (スピーカー式)
- モバイルバッテリー ×3
- 充電式乾電池 ×30本(普段から使用)
- 乾電池×10本(災害時用に保管)
- ポータブル電源 270Wh (災害時用)
- ポータブル電源 1500Wh (普段から使用)
- 太陽光パネル 100W 折りたたみ式(災害時用)
- 太陽光パネル 400W(普段から使用)
照明やラジオなどの小型家電は、私の家ではバッテリー充電式または充電式乾電池でそろえるのが良いと考えています。その理由はこちら。
- 充電式なら普段の生活でも気軽に使える
- 電池を買い足す必要がなく、コストを抑えられる
- わが家は太陽光発電があるので、停電時でも充電に困らない
乾電池式だと「非常用だから普段はもったいなくて使わない」ということになりがちですが、充電式なら繰り返し使えるのでムダがありません。乾電池の買い替えや保管の手間も省けます。
また、わが家では小型の太陽光パネルを使って日頃からバッテリー類を充電しています。小さなパネルでも携帯電話やバッテリーの充電には十分な電力が得られるので、災害用に一枚備えておくと安心です。
とはいえ、乾電池式にも良さがあります。
- 長期保存しても安心して使える
- バッテリーの劣化を気にしなくていい
- 発電システムを持っていなくても使える
それぞれにメリットがあるので、ご家庭の環境に合わせて組み合わせて準備するのがベストだと思います。
衛生・生活用品
- ビニール手袋 ×200
- ポリ袋45L ×100
- 小さなビニール袋 ×200
- 水回り用ゴム手袋 ×2
- 作業用ゴム手袋 ×2
- 軍手 ×20セット
- ティッシュペーパー ×50
- ウェットティッシュ ×20
- 大人用マスク ×200
- 子供用マスク ×100
- アルコール消毒液 ×20
- 絆創膏 ×20
- 傷口用消毒液
- 湿布薬 ×20
- 虫除け用品
- 紙コップ ×100
- 紙皿 ×50
- 割り箸 ×100
- 使い捨てスプーン×20
- 使い捨てフォーク×20
普段から使えるものばかりですが、「肝心の災害時にストックがないじゃん!」というのを防ぐために別で保管するようにしています。
ビニール手袋や袋類は多めに用意しておくのがおすすめです。手洗いや皿洗いが出来ない日が続くことを考えて、衛生的に使い捨てにできる手袋や袋があると安心です。
調理
- ガスボンベ ×10本 (普段使い用とは別に災害用で保管)
- カセットコンロ ×1
- ライター ×2
- 食品用ラップ ×3本 (普段使い用とは別に災害用で保管)
- 生ゴミ乾燥機 ×1(普段から使用)
「生ゴミ乾燥機」はわが家では普段から毎日使っているもので、生ゴミの水分を飛ばして乾燥させることで生ゴミ特有の嫌なニオイが出なくなるようにする機械です。これがあれば災害時にゴミ回収がされない日が続いても異臭や虫の問題に困らないようになります。
生ゴミ乾燥機があれば1ヶ月間ゴミ出ししなくても全く困らずに済みます。
寒さ対策・暑さ対策
- ブランケット用アルミシート ×4
- 床用アルミ保温シート ×4
- カイロ ×20
- うちわ
- ハンディ扇風機
- 冷感タオル
ポータブル電源があったとしても、消費電力が高く継続して電力を使うエアコンや熱器具は停電時に使うことはできません。そのため熱中症対策や寒さ対策は命に関わる重要な項目です。
特に高齢者や子ども、持病のある方がいる家庭では優先的に備えておくことをおすすめします。
文具
- メモ帳
- 筆記用具
- マジックペン
- ハサミ
- カッター
災害時には家に貼り紙をして安否を周囲に知らせることが救援活動の効率化に良いとされています。見やすい黒マジックで書くのが良いので用意しておくといいかもしれません。
修繕・備え
- ブルーシート ×1
- ホイッスル ×2
- 折りたたみ式バケツ ×1
- レインコート ×4
- 長靴 ×4
- スリッパ ×4
- ガムテープ ×1
- 養生テープ ×1
ホイッスルは万が一閉じ込められた際に自分の居場所を知らせる重要な道具です。バケツ・レインコート・長靴は水害や後片付けの場面で、ガムテープ・養生テープは修繕や応急処置にと、いざというときにあると助かるかもしれないアイテムです。
スリッパは家では使わないという人でも、避難所に移動すると必要になるかもしれないので用意しておくのがおすすめです。
現金
- 千円札 ×10
災害時は電子決済やATMが使えなくなるおそれがあるので、家に現金を少しだけ置いておいて買い物ができるように備えておくとよいでしょう。
近所のスーパーも普段はプリペイドカードにチャージする方法で会計していても、災害時には現金のみの取り扱いになる可能性もあります。過去の東日本大震災や熊本地震ではコンビニやスーパーが手打ちでレジ会計をして営業を続けたという例が多数あります。
1万円札のような金額の大きなお札ではなく、使う時のことを考えて千円札で用意するほうがいいと思います。
トイレ用品
- トイレを流す時用の水 180L
- トイレ凝固剤 ×150
- トイレットペーパー ×50
- 生理用品 ×20
- 子ども用オムツ ×60
- おしりふき ×10
わが家では普段から トイレ用の水をペットボトルに保管 しています。
飲み終わったあとの1.5Lのミネラルウォーターの空きボトルに水道水を入れてストックしておくのです。
断水が起きたときでも、この水をトイレのタンクに注げば、普段通りに水を流すことができます。
飲み終わったペットボトルを再利用するだけで費用もあまりかからない、とても手軽な備え方です。
これが120本あって180Lになるのですが、それだけあってもまだ1週間満足にトイレを使えるわけではありません。
| 1日に流す回数 | 継続できる日数 |
|---|---|
| 12回 | 約2.5日 |
| 8回 | 約3.8日 |
| 4回 | 約7.5日 |
トイレ1回で使う水の量が6Lだとすると、180Lで流せる回数は30回です。思ったよりも少ないですよね。
最新型の節水便器であれば1回あたりの水の量が4Lになり、流す回数を増やすことができます。
わが家は水を流す方法だけでは長期間耐えるのが難しいと感じたため、「トイレ凝固剤」も併用することで乗り切ろうと考えています。ボトルの水と凝固剤の組み合わせは災害規模に合わせて柔軟に変えることが必要です。
災害による断水の期間
- 停電・・・復旧まで1~3日程度
- 台風・・・復旧まで1~3日程度
- 洪水・・・復旧まで数日~1週間ほど
- 大地震・・・復旧まで1ヶ月~2ヶ月ほど
数日で終わる断水であれば自分たちでなんとかなりますね。また数週間以上続く断水の場合は行政からの支援が入りますので、まずは「最初の1週間は自分で耐える」という形にしておけば、あとは少しずつ支援をいただいて生きていけるのかなと考えています。
トイレ凝固剤を使う個数の目安
| 期間 | 1人で必要な数 | 家族4人の場合 |
|---|---|---|
| 1日 | 5個 | 20個 |
| 3日 | 15個 | 60個 |
| 5日 | 25個 | 100個 |
| 1週間 | 35個 | 140個 |
トイレ凝固剤は一人1日5回を目安に数を揃えます。保管にスペースをたくさんとるわけではないので予算があればたくさん用意しておくといいと思います。
トイレ対策は「水」と「凝固剤」どっちがいい?
それぞれのメリット・デメリットをまとめてみました。
【ボトルに汲んだ水を使う場合】
水を使って流す方法なら、普段と同じようにトイレを使えるので「ニオイ」や「使い勝手」の心配がありません。
しかも、あらかじめペットボトルなどに水を汲んでおくだけなので、特別なグッズを購入する必要もなく、金銭的な負担もほとんどありません。
とてもシンプルですが、断水時には大きな安心につながる備え方です。
【凝固剤を使う場合】
凝固剤は購入の初期コストはかかりますが、大量の水をストックしておかなくてもいいので、家のスペースを圧迫せずにすみます。
ただし、使った後の排泄物はトイレに流せないため、ゴミとして一時的に保管しなければなりません。このときにどうしても気になるのが「ニオイ」です。
袋を固く縛っても、アンモニアなどニオイのもとになる分子はとても小さいため、袋の素材を通り抜けてしまい時間が経つと外に漏れ出してきます。最初は臭わないと思っても、数日経つと少しずつ漏れてきて1週間後には耐え難くなるイメージです。うちは子どものオムツでこれを毎日体験しています。
水は分子が大きいので袋を通り抜けませんが、ニオイの分子は小さいため袋の素材をすり抜けて外に漏れてしまいます。
そのため、使用後の袋はなるべく室内には置かず、ベランダや庭などに出して保管するなどの工夫が必要になります。この点も踏まえて準備しておくと安心です。
飲み水
- 飲み水 100L
わが家では飲み水として1.5Lが6本入ったケースを12箱用意しています。それでも家族4人で使うと約8日で使い果たしてしまいます。
| 1人1日分 | 4人×3日分 | 4人×7日分 |
|---|---|---|
| 3L | 36L | 84L |
清潔な水は飲むためだけでなく料理や手洗いなどでも使うので多めに用意しておきたいところです。
食べ物
- パックご飯 ×24食
- 袋ラーメン ×15食
- ツナ缶 ×20個
- レトルトカレー ×20食
- カンパン
- 麦茶パック ×30回分
- その他、缶詰・乾麺・お菓子など
わが家では食品は普段から消費しつつ補充する「ローリングストック」を基本にしています。
ローリングストックとは?
ローリングストックとは、普段から食品や日用品を少し多めに買い置きしておき、賞味期限を考えて古いものから順に消費し、消費した分を買い足すことで、常に一定量を備蓄する方法です。
わが家では、少し多めに準備して今は1か月分ほどの食料を備蓄しています。
みなさんも備蓄を用意する時には、災害時に実際に調理する場面をイメージしながら用意しておくのがおすすめです。
わが家はポータブル電源があるのでパックご飯は電子レンジで温められますし、カップラーメンも電気ケトルでお湯を沸かせばすぐに食べられます。
パックご飯は電子レンジが使えない状況では温めにくく、湯煎で作ることもできますが、必要な水の量や加熱時間を事前に確認しておかないと困ってしまうかもしれません。災害時はネット検索ができない可能性もあるので、手元にメモを残しておくと安心です。
人によっては必要かもしれないもの
上で紹介したのは私の家の場合の持ち物ですが、人によってはこんなものも必要になるかもしれません。
- 粉ミルク
- 離乳食
- 大人用 紙パンツ
- 子ども用 夜用パンツ
- 飲み薬・塗り薬
- 保湿クリーム
- 加湿器(電気不要のもの)
- ペット用品
- コンタクトレンズ用品
「全ての家庭に必要ではないけれど、家庭の状況によっては“命綱”になるアイテム」というものがあります。停電や断水の中で過ごすことを想像しながら、家族みんなで話し合う時間を持つことも、とても大切です。
備蓄の保管場所
わが家は現在 一戸建てに住んでおり、2階の一部屋を物置部屋として使っています。以前は賃貸に住んでいましたが、そのときも同じように一部屋を物置として、日常のストック品や防災用品をまとめて管理していました。洗剤・トイレットペーパー・ティッシュ・水など「すぐには使わないけれど保管しておきたいもの」をこの部屋で一括して管理しています。
庭の物置に置けるものもありますが、外は高温多湿になりやすく品質が劣化する可能性があるため控えています。また、浸水のリスクも考えると、家の2階に保管する方が安心かなと思っています。
わが家の災害対策まとめ
- 在宅避難前提なので「量多め」
- 災害時だけでなく普段から使う物も多い
- 2階の一室を物置化し、災害用品と日用品のストックを一括管理
- ポータブル電源と太陽光パネルで電気対策もあり
防災対策というと「ラジオ・ライト・水など一式あれば安心」と考えがちですが、それだけでなく食料や水トイレなど人数×日数分の用意が非常に重要です。行政が推奨するのは「最低3日分」ですが、実際の災害時には1週間以上の備えが安心です。
避難スタイルによっても必要な備えは変わるため、自宅で過ごすのか、避難所に行くのかをまず想定するようにしましょう。読んでくださったあなたも、ご家庭の人数や生活スタイルに合わせて無理のない範囲で備蓄を整えていただければと思います。