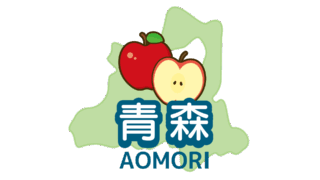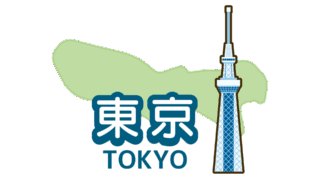突然の停電──。
「冷蔵庫の中の食材、どれから食べればいいの!?」と焦った経験はありませんか?
停電中は冷蔵庫が冷えなくなるため、時間が経つほど食材が傷みやすくなります。
そこで今回は、停電時に「食べるべき順番」をわかりやすくランキング形式で紹介します。
限られた時間と食材をムダにしないためにも、いざというときの判断基準を知っておきましょう。
1位 「生の肉・魚」
生の魚や肉は表面に菌がついているのですが、いつもはこれを冷蔵保管によって繁殖を抑えています。これが停電で温度が上がってしまうと菌が増殖して食中毒リスクが高まります。
特に10℃~50℃の環境で菌が繁殖しやすいので、そうなる前に早めに調理して食べることが推奨されます (参考: 厚生労働省)。
『アメリカ合衆国農務省(USDA)の食品安全検査局(FSIS)』の情報では、停電後の冷蔵庫は扉を開けなければ最大で約4時間は食品を安全に保てるとされています。
ただし、夏場のように室温が高い時期には、その時間がもっと短くなることもあります。特に生の肉や魚など傷みやすい食材は、できるだけ早めに食べるようにするのが安心です。
消費目安:停電後 2時間以内 に消費
2位 「牛乳」
牛乳は栄養価が高く、菌のエサになる成分が豊富に含まれています。それに加えて液体ということも相まって菌が全体に広がりやすく、少し温度が上昇するだけでも急速に菌が増殖して傷みます。
開封済み・未開封にかかわらず、停電時は優先的に消費するのが安心です。特に夏場など室温が高いときは注意してください。
消費目安:停電後 2時間以内 に消費
3位 「たまご」
卵は生モノなので家庭では冷蔵庫で保管するのが基本です。実際、食品衛生の観点からも冷蔵保存が推奨されています。
それなのに、スーパーで常温で売られているのはなぜでしょうか。
これは卵の特性に理由があります。卵の殻には呼吸のための小さな穴が無数にあり、冷たい卵を常温に戻すと表面に結露がついてしまいます。その水滴から雑菌が入り込み、傷みやすくなるのです。
もしスーパーで冷蔵販売すると、買ってから家に帰るまでに卵が結露してしまうかもしれませんね。そこで、販売時はあえて常温にして結露を防いでいるというわけです。
この仕組みを考えると、停電で冷蔵庫が止まり卵が常温に戻るときにも同じ注意が必要です。特に停電後は生で食べるのは避け、加熱調理にすると安全性が高まります。
消費目安:停電後 2~4時間以内 に消費
4位 「作った料理の残り」
昨日の晩ごはんの残りなどが冷蔵庫にある場合、これもできるだけ早めに食べきるようにします。
すでに加熱調理してある料理であっても、常温に近い温度帯になると菌は再び増殖していきます。つまり「加熱済み=いつでも安心」ではありません。
料理はできるだけ出来立てを食べ切るのが一番安全ですが、残す場合は粗熱を取ったらすぐに冷蔵庫で保管し、菌が増えやすい温度帯(およそ10〜50℃)に長く置かないことが大切です。
そこで停電時にもこの温度帯にならないように注意が必要となります。
再加熱可能であれば、中心温度75℃以上で1分以上加熱してから食べると安心です。
消費目安:停電後 4時間以内 に消費
5位 「開封済みの飲み物・食べ物」
- 飲みかけのジュース
- 開封済みの鮭ビン
- 封を開けたチーズ
- ジャムの残り
- ヨーグルトの残り
たとえ口をつけずにコップで飲んだり、きれいなスプーンですくって残した食べ物だとしても、空中からの菌やカビ胞子の混入は避けられないので菌の増殖リスクがあります。
ドレッシングの残りや調味料系はさすがに一気に使い切ることはできないのですが、せめてすぐに食べられるものだけは救ってあげたいですね。
消費目安:停電後 4時間以内 に消費
6位 「野菜・果物」
野菜や果物には、土や表面の水分と一緒に菌やカビ胞子が付着していることがあります。
停電が始まるとそのあと水道も止まる可能性があるため、まだ水が出るのであれば先に洗っておくと安心です。
ただし、洗ったあとは水気をしっかり拭き取り、できるだけ早めに食べ切るようにしましょう。
玉ねぎ・じゃがいも・リンゴなどのように「丸ごと未カット」の状態であれば比較的長持ちしますが、一度カットされたものは断面から劣化が進むため、早めに使い切る意識が必要です。
また、野菜・果物の劣化は収穫からの経過日数や保存方法などによっても変わるため、目安時間にとらわれず鮮度を個別で見ながら判断することも大切です。
消費目安:停電後 4~6時間以内 に消費
7位 「未開封の要冷蔵食品」
未開封の食品は、工場で衛生管理されて酸素を遮断して密閉包装されているため、菌やカビの増殖リスクは低めです。
ただし要冷蔵品は温度が上がると劣化や風味の変化が進むので、長時間の放置は避けたいところです。
一方で常温保存できる未開封食品が冷蔵庫に入っている場合は停電後でも安全に食べることができます。ペットボトルの飲料やお酒など、開ける前でも飲む時のために先に冷やしておくことがありますよね。これらは停電時に焦って消費する必要はありません。
要冷蔵品の消費目安:停電後 4~6時間以内 に消費
8位 「アイス・氷」
アイスや氷は溶けると形を保てなくなり、冷凍庫内でドロドロになってしまいます。そのため「早めに処分しなければ」と思うかもしれませんが、実は結構余裕を持って消費できます。
冷蔵庫に比べて冷凍庫は保温性が高く、急激に温度が上がらないように設計されています。扉を開け閉めしなければ長時間マイナス温度を保つことが可能です。
『アメリカ合衆国農務省(USDA)の食品安全検査局(FSIS)』によると、
- 冷凍庫が満タンの状態なら 約48時間
- 半分程度なら 約24時間
食品を安全に保存できるとされています。
とはいえ、氷やアイスは溶けてしまうと後処理が大変になるため、停電中の状況によっては早めに消費しておくのも安心です。
消費目安:停電後 12時間以内 に処理
9位 「冷凍庫の食品」
冷凍庫は保温性が高く、ほかの凍った食材が保冷剤の代わりとなることもあって食材が比較的長持ちしますが、
- 消費のために開けしめする
- 中身がだんだん減っていく
これらを考えると24時間以内に冷凍庫内はすべて消費するのが安心です。
消費目安:停電後 24時間以内 に消費
【別枠】口をつけたペットボトル飲料は?
口を直接つけて飲んだペットボトル飲料や缶ジュース・缶ビールなどは、どのタイミングで飲み干すべきでしょうか。
答えは最優先です。というのも、そもそも冷蔵庫保管しても菌が増殖することがあるからです。
冷蔵庫の低温の中でも増殖できる
冷蔵庫の温度は通常0℃~4℃ですが、口内の一部の菌はこの低温でも耐性があり、ゆっくりと増殖することがあります。
実際、『公益財団法人 鹿児島県学校給食会』の実験では、口をつけたペットボトルのミネラルウォーターを冷蔵庫に入れても、菌が少しずつ増殖していく様子が確認されました。
26℃の常温や37℃の高温では、さらに菌の増殖が急激に進むことがわかっています。
冷蔵庫に入れていても増える菌が、停電で温度が上がるとさらに増えることを考えると、口をつけた飲み物は真っ先に消費したいですね。
飲み物による増殖の違い
『宇都宮市衛生環境試験所』では、ミルクコーヒー・麦茶・緑茶・スポーツ飲料・果汁100%オレンジジュースを対象に、30℃で48時間保存したときの菌の増え方を調べています。
その結果、一番菌の増殖が多かったのはミルクコーヒー。24時間後には1000万個、48時間後にはなんと3億個にまで増殖しました。糖分やタンパク質を栄養として菌が増えたと考えられます。
2番目に増殖が多かったのは麦茶。麦茶には炭水化物が多く含まれるので、それを栄養として増えたと考えられます。
一方で、緑茶・スポーツ飲料・オレンジジュースは菌が減少するという意外な結果に。緑茶に含まれるカテキンの抗菌作用や、スポーツ飲料やオレンジジュースの酸性環境が菌の増殖を抑えたようです。
ただし、だからといって「安心して放置していい」というわけではありません。飲み物は直接口をつけずにコップに移す、あるいは早めに飲み切るなど、普段から少し気をつけておくと安心ですね。
時間がたったものは捨てる
停電してから時間がだいぶ過ぎてしまった場合、もったないないとは思いますが捨てる判断も必要です。
- 賞味期限内だけど変なニオイがする
- 変な味で舌がピリつく感じがする
- 容器が膨張している
- 冷蔵庫に入れる前、常温で放置した時間が結構あった
- 停電前の時点ですでに開封後の時間が経っている
こうした場合は無理に食べずに捨てることも必要です。
停電時つまり災害などの非常事態の状況の下で、お腹をこわす、病院にいかなければならない、という方がよっぽど大変な思いをすることになりますからね。
妊婦・幼児・高齢者などは要注意
停電後の食材管理で特に注意が必要なのは、妊婦さんや小さな子ども、高齢の方など、食中毒に対する抵抗力が弱い人たちです。
わずかな菌の増殖でも体調を崩してしまう可能性が高いため、少しでも「怪しいかな」と感じた食品は思い切って処分するのが安全です。
まとめ
停電が起きると、冷蔵庫や冷凍庫の中身は思った以上に早く劣化してしまいます。まずは保存時間の目安を把握し、食べる順番を意識すること。
迷った時は「食べない勇気」を持ち、安全を最優先に考えましょう。