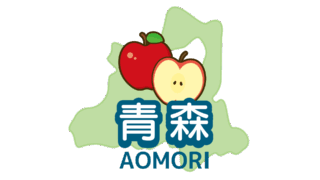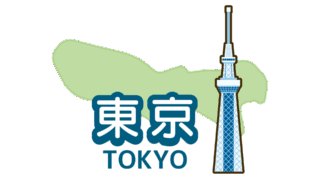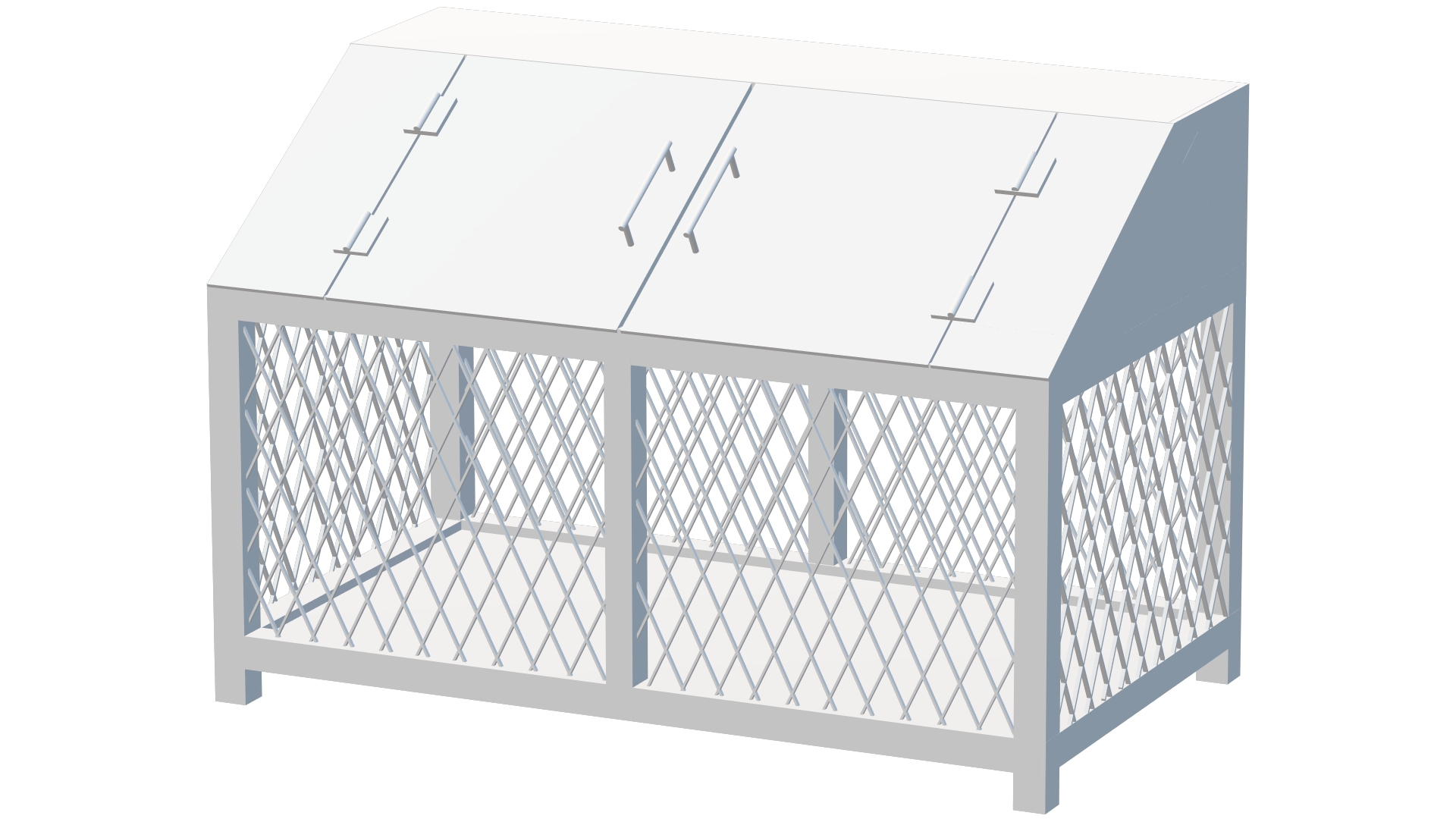「町内会・自治会に加入していなくてもごみ出しはできる」
「ゴミ出しは市民の権利で無料だ」と主張する人がいます。
一方で、多くの地域では、ごみステーションの維持管理や清掃が町内会・自治会の会費と労力によって支えられています。
そのため、未加入者が同じ場所を利用することに対して、不公平感や不満を抱く人も少なくありません。
そこで今回は、
ごみステーションを無断で使うと、法的に問題になるのか?
この点について、実際の法律をもとに整理していきます。
手放したら所有権は放棄される?

ゴミを捨てると、民法第239条第1項に従って捨てた時点で所有権は放棄したとみなされます。
ですが、だからといって置いた場所での責任がなくなるわけではありません。
- 私有地(他人の家の庭や山、マンションのゴミ捨て場など)に無断でゴミを捨てると、廃棄物処理法第16条の不法投棄にあたる
- コンビニのゴミ箱に家庭ごみを捨てるのも、同じく他人の土地になるので不法投棄にあたる
- 5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が科される可能性あり
したがって、ゴミステーションが私有地に設置されている場合、許可なくゴミを出すと「不法投棄」とみなされるおそれがあります。
💡大事なポイント
- 私有地に捨てる場合は不法投棄
- マンションでは住民以外が捨てると不法投棄
公道上のゴミステーションの場合は?
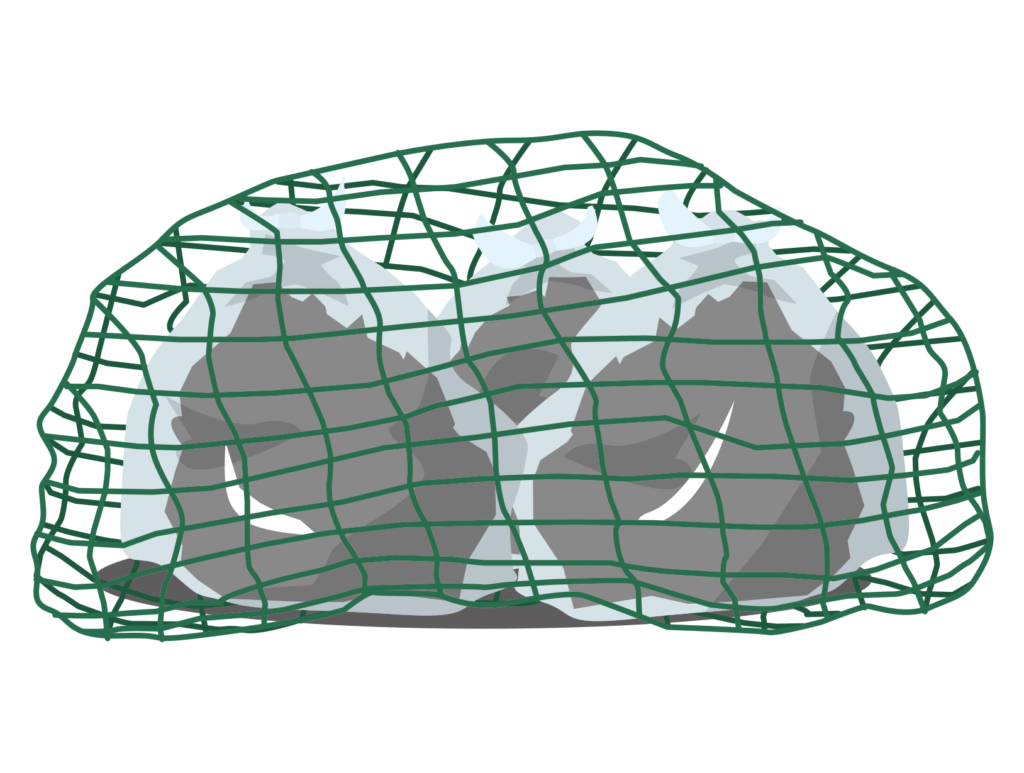
歩道や車道上に設置されたゴミステーションの場合はどうでしょうか。
廃棄物処理法の第16条によると「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されています。
この「みだりに」という言葉の解釈がポイントです。
法律上、不法投棄というのは “正当な権限なしに・適正手続きを経ずに・許可された場所でない場所へ廃棄物を捨てる行為” と捉えられています。
したがって、ルールを守って捨てられたゴミは不法投棄にはあたらない、ということになります。
- 公道上で、行政がゴミ出しを許可している区画内で捨てられたゴミは、法律上問題なし
- ゴミ出しの曜日や時間を守り、分別も正しく行う場合は、不法投棄にはあたらない
つまり、公道上のゴミステーションの場合は、町内会員・自治会員であるかにかかわらず、ルールを守っている限りは誰でもゴミを捨てられるということになります。
💡大事なポイント
- 公道ならルールを守って出せば不法投棄にならない
しかしここで重要なのは、“不法投棄にだけは当たらない”ということ。ほかの法律やルールに引っかかっていたらアウトです。次の項目もご覧ください。
ゴミステーション維持管理の義務

家庭ゴミの出し方に関する法律はまだあります。廃棄物処理法の中の別の条項について見ていきます。
ゴミ回収の責任と住民の責任
ゴミ回収をするのは誰なのか、住民はどう行動すべきか、というルールが廃棄物処理法の第6条第2項に記載されています。
ここの内容が長くて難解なので噛み砕いて要約すると、ポイントは次の3つになります。
- ゴミの回収・運搬・処分は市町村(行政)が行う
→ 市民が出したゴミを回収するのは地方自治体の仕事です。 - 行政はゴミの回収・運搬・処分を外部に委託できる
→ 業者にお願いすることも可能です。 - 土地・建物の占有者は、ゴミの分別・保管を行い、行政に協力する義務がある
→ 「占有者」は所有者ではなく、土地や建物を利用している人という意味。
→ ゴミステーションの場合は、ゴミを出している人たちを指します。
まず①では、ゴミの回収は地方自治体が行うもので、回収は行政の義務であることが示されています。
①だけを読むと、「ゴミは行政に回収されて当然」ともとれます。
しかしそのあと③では、「ゴミを出す人は、自分で分別や保管をして回収処分に協力しなければならない」とも書かれています。
利用者がゴミを管理する
ゴミを回収するのは行政の仕事ですが、回収されるまでの間のゴミ管理・回収されなかったゴミの管理は利用者自身の責任です。
このときの「利用者」は、町内会・自治会に加入しているかどうかに関係ありません。
- 非会員でもゴミは出せる
- ゴミを出した時点で、その人は「利用者」として認められる
- 利用者は、分別や保管を意識して行う必要がある
この観点から、ゴミステーション方式を採用している地域では、町内会員かどうかに関係なく、利用者が協力してゴミを管理するという考えにつながります。
過去に裁判所が下した判断
廃棄物処理法第6条にあるように、ゴミを出した人(占有者)は、ゴミの分別・保管に協力しなければならないというルールがあります。
ゴミを出して「ハイ終わり」ではなく、その後ゴミがきちんと回収されたかどうかや美観維持のための掃除・壊れたステーションの補修などを含めてゴミ出しスペースを管理する必要があります。
町内会のゴミステーションは、会員が費用を出し合い、当番制などで維持しているからこそ、地域の住民が安心して利用できています。
そのため、その場所を利用するのであれば、維持や管理を担っている町内会・自治会に協力するのは当然のことといえます。
こうした事情を考えると、裁判所が「ゴミステーションを利用する人には町内会・自治会への協力義務がある」と判断するのも、十分に妥当であると言えるでしょう。
↓非会員と町内会・自治会が争った実際の裁判例はこちらで紹介しています。
まとめ
- 分別や時間のルールを守って指定の公共スペースに出すゴミは不法投棄ではない
- 非会員でも捨てられるが、同時にゴミ出し利用者としてみなされる
- ゴミ捨て場の維持管理はゴミを捨てた人の責任で義務
ゴミ捨て場を使う以上、利用者の一人としての責任も生まれます。ゴミ捨て場を清潔に保ったり、マナーを守ることは、会員・非会員に関係なく大切なことです。
みんなが気持ちよく使うためには、「自分も利用者の一人」という意識をもって、地域全体で協力しながらきれいな環境を保っていく必要があります。