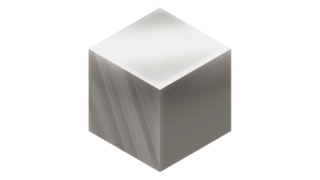SNSなどを見ると、「竹島は日本の領土だ」「日本のものなのだから国際裁判でも当然勝てる」といった意見を多く見かけます。
日本政府(外務省)も、公式見解として竹島は日本固有の領土であると主張しています。
そのため、多くの日本人がこの問題を「すでに結論が出ている話」だと受け止めているかもしれません。
しかし、仮にこの問題が国際裁判に持ち込まれた場合、同じ結論が出るとは限らないのが現実です。
本記事では、感情論ではなく、
- 竹島をめぐる歴史的経緯
- 国際裁判で重視される判断基準
- 過去の国際裁判の前例
これらをもとに、
「竹島は本当に日本の領土と言い切れるのか」を冷静に考えていきます。
かつての竹島は「国境の島」ではなかった
竹島は、日本で江戸時代から漁業の目印や寄港地として利用されてきました。
特に現在の島根県側の漁民が、アワビ漁や漁場探索の際に渡海していた記録が残っています。
一方で、この時代の竹島は無人島であり、恒常的な居住や行政管理が行われていたわけではありません。
当時は現在のような「国境の島」という認識はなく、あくまで漁業活動の一環として利用されていたに過ぎませんでした。
韓国側についても状況は同様です。
当時の朝鮮王朝において、竹島 (韓国名:独島) は行政的に管理された領土とはされておらず、恒常的な居住や統治の記録は確認されていません。
重要なのは、この時代の東アジアでは、無人島を現代のように厳密な国境線の一部として捉える感覚が一般的ではなかったという点です。
海は原則として自由に利用される空間と考えられ、漁業活動が国境問題に直結するという意識は、まだ形成されていませんでした。
1905年 竹島が日本領に編入された年
竹島問題を考えるうえで、必ず触れなければならないのが1905年です。
この年、日本政府は竹島を島根県に編入する閣議決定を行いました。
なぜ1905年だったのか
19世紀末から20世紀初頭にかけて、列強各国は
- 無人島などの誰のものでもない土地を
- 国家としての意思を示し
- 行政的に編入する
という方法で領土を確定させていきました。
日本も例外ではなく、竹島についても
を背景に、1905年に正式な手続きを取っています。
日本側が行った具体的な手続き
1905年、日本政府は次のような流れで対応しました。
- 島根県からの要請を受け
- 竹島が他国の領有下にないことを確認
- 閣議決定により島根県への編入を決定
- 県告示によって公示
これは、当時の国際法上、領土取得として一般的とされていた平和的手続きに沿ったものです。
少なくとも「秘密裏に奪った」「軍事力で排除した」といった性質のものではありません。
当時の韓国側の反応
1905年当時、韓国側からこの編入に対する公式な抗議や外交的異議は確認されていません。
背景としては、
- 竹島が無人島であったこと
- 海は基本的に「自由に利用できるもの」という意識が強かったこと
- 島一つで将来の海洋資源や排他的権利が左右されるという発想が、まだ一般的でなかったこと
などが挙げられます。
つまり当時は、「島を押さえること=海の権利を確保すること」という現代的な感覚は、ほとんど存在していなかったと考えられます。
1905年~1945年 日本領で特に問題なかった時代
- 島根県の管轄下で日本人漁民が利用を継続
- 国際問題として取り上げられることはほぼなし
- 日本・韓国双方の積極的な領有権争いもなし
この「争いがなかった」という事実は、後の国際法判断で一定の意味を持つ可能性があります。
1951年~1952年 サンフランシスコ平和条約
日本が1945年に敗戦したあと、1951年9月のサンフランシスコ平和条約で、日本が放棄すべき領土が列挙されました。
その中に南樺太や朝鮮半島を放棄することが盛り込まれましたが、竹島の名前は明記されませんでした。
韓国は竹島を韓国領土に含めるようにアメリカに要請を出しました。
しかしアメリカはこれを採用せず、竹島は日本管轄下にあるとの立場を示しました。
韓国からの要請に対し返答した米国務省文書(ラスク書簡)では、
never treated as part of Korea
「竹島は韓国の領土として扱われたことはない」
since about 1905, has been under the jurisdiction of the Oki Islands Branch Office of Shimane Prefecture of Japan
「約1905年以降は日本の島根県隠岐支庁の管轄下にある」
とする認識が示されています。
英文引用
“As regards the island of Dokto, otherwise known as Takeshima or Liancourt Rocks, this normally uninhabited rock formation was according to our information never treated as part of Korea and, since about 1905, has been under the jurisdiction of the Oki Islands Branch Office of Shimane Prefecture of Japan. The island does not appear ever before to have been claimed by Korea.”
— Dean Rusk, U.S. Under Secretary of State for Political Affairs, to Korean Ambassador Yang Yu‑Chan, August 10, 1951
和訳例
「竹島(Dokto、別名TakeshimaまたはLiancourt Rocks)について、通常は無人の岩礁であり、私たちの情報によれば、これまで韓国の一部として扱われたことはなく、約1905年以降は日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。これまで韓国によって領有権が主張された記録もありません。」
— 1951年8月10日、ディーン・ラスク米国務次官補から韓国大使 梁裕燦 宛
参考URL: 外務省「竹島関係資料」
https://www.cas.go.jp/jp/ryodo_eg/shiryo/takeshima/detail/t1951081000101.html
1952年 韓国が実効支配を開始
サンフランシスコ条約が発効するのは1952年4月以降ですが、それが発効するまでの期間中に韓国側は大きな行動に出ます。
1952年1月、韓国大統領 李承晩は「李承晩ライン」を発表し、竹島周辺を自国の支配下としました。
この線は国際条約に基づかない一方的な設定で、竹島が韓国側に含まれています。
当時、日本はまだサンフランシスコ平和条約の発効前であり、完全な主権を回復していない過渡期にありました。この政治的・法的な空白期を突く形で、韓国は行動に踏み切ったと考えられています。
韓国側の視点
韓国側の立場では、李承晩ラインの設定と竹島の管理は自国の海洋資源保護のための措置と位置付けられています。
- 当時、朝鮮漁民も竹島周辺海域を利用していた
- 日本漁船による資源の過剰搾取を防ぐ意図があった
- 国際法よりも国内法・独立国家としての権利行使を優先した
日本漁船の排除と事件の発生
李承晩ライン設定後、韓国は竹島周辺海域での監視や取り締まりを強化しました。
この際、日本漁船が海域に入ったとして、漁船の拿捕や乗組員の一時拘束が行われ、船同士の衝突事故も起きました。
韓国側は、国内法に基づき自国の海域を管理する一環として行った措置と位置付けています。
日本政府が行った抗議
日本政府は、韓国政府に対して
「李承晩ラインおよび竹島周辺における行動は、日本の領土権を侵害している」
という趣旨の外交ルートを通じた公式抗議(ノート・ヴェルバル)を行いました。
また、これ以降も数年にわたり
- 外交ルートでの抗議書の提出
- 韓国政府に対する抗議の公式声明
- 国際社会向けの説明
などの形で、「竹島に関する韓国の行為は、国際法上認められない」という立場を繰り返し示しました。
1954年~ 韓国による施設の建設と常駐開始
韓国は、1952年に李承晩ラインを宣言して竹島を実効支配し始めた後、管理体制を強化するために施設や建物を設置しました。
- 1954年頃:韓国警備隊が常駐し、簡易施設を設置
- 1960年代〜1970年代:倉庫、桟橋など施設を整備
- 1980年代以降:航空標識や通信設備を設置し、管理の存在を明確化
1954年~ 日本が国際裁判所(ICJ)での解決を提案
1954年、日本政府は竹島の領有権を明確にするため、ICJ(国際司法裁判所)への付託を韓国に提案しました。これは、第三者の公平な立場から竹島が日本領か韓国領かを判断してもらうための申し出でした。
しかし、韓国側はこれを拒否しました。ICJでは、両国が同意しなければ裁判は開かれないため、この提案は実現しませんでした。
同様に、1962年と2012年にも日本は裁判や話し合いの場を求めましたが、韓国はすべて拒否。
韓国の立場では「日韓間に領土問題は存在しない」とされ、竹島(独島)は自国のものとして扱う姿勢を貫いています。
ICJへの付託提案は「法的手続きによる解決を求める意思表示」が日本側にあるとして、後の領有権判断で重要な証拠となる可能性があります。
ただし、提案した回数は合計で3回と少なく、1962年と2012年の間には50年という大きな間隔が空いているのが実情です。この点は裁判で少し日本側に不利に働くおそれがあります。
国際裁判所の領土判断基準
領土紛争が国際裁判所(ICJ)に持ち込まれた場合、裁判所は法的根拠と事実上の管理状況の両方を総合的に評価して判断します。以下のような基準が重要とされています。
1. 歴史的権原(Historical Title)
- 国や国家が過去にその領土を正式に取得・支配した証拠を重視
- 古文書や条約、行政文書などが典型的な根拠になる
竹島について、日本と韓国の双方が「自国の島だ」と認識していたこと自体は、国際裁判所での決定的な判断材料にはなりません。どちらが早く島を認識していたかも、問題にはなりません。
裁判所が重視するのは、あくまで 国家による公式な手続きや管理の実態 です。
そのため、1905年に日本が竹島を島根県として編入した際の手続きや文書が、歴史的権原の一部として高く評価される可能性があります。
2. 実効支配(Effectivités)
- 実際にどの国家が継続的・平和的に統治や管理を行ってきたかを評価
- 単なる宣言だけでなく、施設の設置、警備、行政管理、住民や漁民への規制なども含む
- 長期的に安定した管理は、法的権原が弱くても領有権の証拠として重要になる
3. 相手国の黙認・抗議(Acquiescence or Protest)
- ある国が長期間支配していた場合でも、他国が抗議を続けていたかが判断材料になる
- 抗議を怠った場合、「黙認した」とみなされることもある
竹島の場合、日本は1952年以降に即時かつ継続的に外交抗議を行っているため、黙認していない証拠になります。
4. 国際法・条約上の根拠
- サンフランシスコ平和条約の条文など、国際条約の扱いも重要
- 条約で明示されていない場合は、条約解釈や附属文書、交渉経過なども裁判所の判断材料になる
日本と韓国の双方の主張
日本側には①「取得の証拠となる行政文書」と③「相手国への抗議」さらに④「国際法・条約上の根拠」があります。
一方で韓国側は、②「長期間の実効支配」があります。竹島の周辺海域を警備と島内の施設設置を行い、実質的に国家の領土として管理・運用を行っています。
ここで重要なのは、どれか一つだけが領土を決める決定的な証拠にはならないということです。
一連の流れを総合し、その上でどちらの領土として相応しいかを国際裁判所では判断します。
また、国際裁判所では過去に下った裁判例も判断基準として重要視されます。
ペドラ・ブランカ事件(2008年)
- 小さな岩礁をめぐるマレーシアとシンガポールの領土紛争
- 歴史的にはマレーシア領だったが、シンガポールが長年管理
- マレーシアが明確な抗議を長期間行っていなかった
- 裁判所はシンガポール領と判断
歴史的にはマレーシア側に一定の根拠がありましたが、「長年の行政管理」と「マレーシアが抗議を怠ったこと」を理由に、島はシンガポール領と判断されました。
エリトリア・イエメン領土紛争(1999年)
- 小島々をめぐる領有権紛争
- 両国が歴史的権原と漁業利用を主張
- 裁判所は「歴史的権原」だけでなく「実効支配」も評価し、島々を分配
たとえば Al Hanish al Kabir(通称 大ハニシュ島) は、地理的にはエリトリアとイエメンのほぼ中間に位置します。さらに1995年にエリトリア軍が侵攻し島を一時的に占拠している中で裁判が行われました。
しかし国際仲裁裁判では、現在進行している一時支配よりも、イエメン側が長年にわたり行ってきた灯台や関連施設への関与、漁業活動の管理といった、平時における継続的かつ安定した関与が重視されました。
これらの要素を総合的に評価した結果、大ハニシュ島の主権はイエメンに帰属すると判断されました。
「実効支配していた歴史」を国際裁判は軽く見ない
国際裁判所は、歴史的権原だけで領有権を決めるわけではありません。
どの国が実際に継続的・平和的に統治や管理を行ってきたかも重要視されます。
施設の設置や警備、漁業規制、灯台や標識の管理など、日常的な行政管理が長期間続いている場合、その国の権利として裁判所は認めやすくなります。
竹島の場合も同様です。韓国は1952年以降、島内への施設設置や警備を通じて長期的に実効支配を行ってきました。
一方で、1952年以降、日本は外交を通じて領有権を主張してきましたが、実際の島の管理や施設の運営は韓国が行っており、日本は現場には関与していません。
武力による支配の開始は国際裁判でどう扱われるか
竹島周辺で韓国が1952年に実効支配を開始した際、一部報道や議論では「漁船の排除など強制的な手段があった」と指摘されています。
もしICJで審理された場合、このような行為は「正当な手続きで得た権利ではない」と評価される可能性があります。
ただし、その後の長期的な管理や施設の設置、警備の継続は「実効支配」として重要視される部分です。
国際裁判所では「支配の手段」と「継続的な管理状況」を区別して評価します。武力や強制行為による開始は否定的に扱われますが、平和的な管理の継続があるかどうかが領有権の判断には大きく影響します。
つまり、支配の開始が一時的に強制的であったとしても、その後の実行支配が全て無効になるわけではないということです。
過去の裁判例からも分かること
先程紹介した「エリトリア・イエメン領土紛争」の例でも、国際仲裁裁判所は、エリトリア側による武力支配について、次のように位置づけています。
- 1995年の軍事占拠は「最近の出来事」であること
- 紛争発生後に行われた、一時的かつ武力による支配であること
- 主権の根拠としては弱いと評価されること
これらを踏まえ、仲裁裁判所は、灯台や施設への関与、漁業活動の管理など、平時における長期的かつ継続的な関与を行ってきたイエメン側に主権があると判断しました。
ここで重要なのは、軍事支配そのものが否定されたわけではないという点です。
仲裁判断を丁寧に読むと、
- 武力行使そのものを違法と断罪した
- 軍事占拠は一切考慮しない
といった書き方はされていません。
あくまで「支配が最近の出来事であり、一時的なものであった」という評価が、主権の根拠として弱いと判断された理由だといえます。
「日本は当然裁判で勝てる」という思い込みは危険
竹島の領有権は、単純に「日本の領土だから当然勝てる」とは言えません。
1905年に日本が島根県に編入した手続きや行政文書は、歴史的権原の一部として評価されます。しかし、それだけで裁判所が領有権を決めるわけではありません。
一方で、韓国は1952年以降、島内への施設設置や警備、漁業規制などを通じて長期的に実効支配を行ってきました。
過去の国際裁判の例からも、長期間の実効支配は裁判所の判断で非常に重要であり、歴史的権原だけでは決定的な要素にならないことがわかります。これは竹島でも同様の可能性があります。
支配実績を積むための戦略の可能性
日本のSNS上では、
「韓国は裁判で負ける可能性が高いと分かっているので拒否しているのでは?」
という見方があり、誤解されやすい状況となっています。
しかし、韓国側の狙いはむしろ、長期の実効支配を積み上げることで権利を強化するために裁判を延ばしている可能性があります。
国際法では裁判の提案を拒否したとしてもペナルティがありません。
そのため、
- 実効支配している側は裁判を急ぐ必要がない
- 裁判を拒否しても法的に不利にはならない
こうした背景から、拒否し続ける戦略が通ってしまいます。
時間が経つほど、実効支配の実績は積み上がっていく
この構造を理解する必要があります。
近年の日本の抗議は控えめ
近年では、抗議の頻度や強度がやや控えめになっています。
この背景には、日韓間の経済関係や安全保障上の配慮が影響していると考えられます。
韓国は日本にとって重要な貿易・投資パートナーであり、強い抗議が経済関係に悪影響を与える可能性があります。
また、両国はともにアメリカとの同盟国であり、米国は日韓協力の維持を重視しています。
そのため、外交的に強硬な対応を控えることで、地域の安定や協力関係を維持する意図が働いていると考えられます。
まとめ
竹島について、日本の主張には一定の法的根拠があります。しかし現状を整理すると、単純に「日本が当然勝つ」とは言えません。
- 1905年 島根県に編入した際には韓国からの抗議は確認されていない
- 1952年 韓国が李承晩ラインに竹島を含めて実効支配を開始した際、日本は外交ルートで抗議を行った
- 以降、韓国は島内施設の設置や警備などを通じて管理を継続し、70年以上の実効支配が続いている
- 国際裁判では、歴史的権原と実効支配の両方を総合的に判断する
- 近年の日本の抗議は、経済・外交的配慮からやや控えめになっている
これらを踏まえると、裁判を行えば必ずしも日本が勝つとは限りません。
重要なのは、平和的な抗議を続けることが、長年の実効支配を積み上げた側の戦略に対してどこまで有効かを、国際裁判の性質を踏まえて冷静に分析することです。
問題を先送りにして放置すると、韓国の長期的な実効支配の事実が積み重なり、国際裁判における評価が韓国側に有利になってしまうかもしれません。
参考文献
日本外務省「竹島」公式解説
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/
韓国外交部 独島(竹島)公式ページ
https://dokdo.mofa.go.kr/m/jp/pds/pdf.jsp
国際司法裁判所(ICJ)公式サイト
https://www.icj-cij.org/
ペドラ・ブランカ事件 判決概要(ICJ)
https://www.icj-cij.org/case/130
エリトリア・イエメン仲裁裁定 概要
https://pca-cpa.org/en/cases/1/