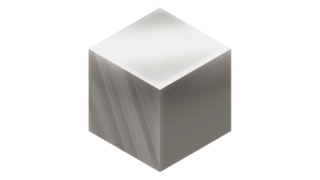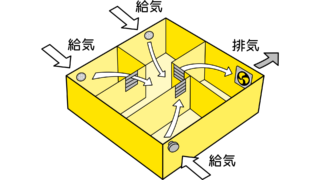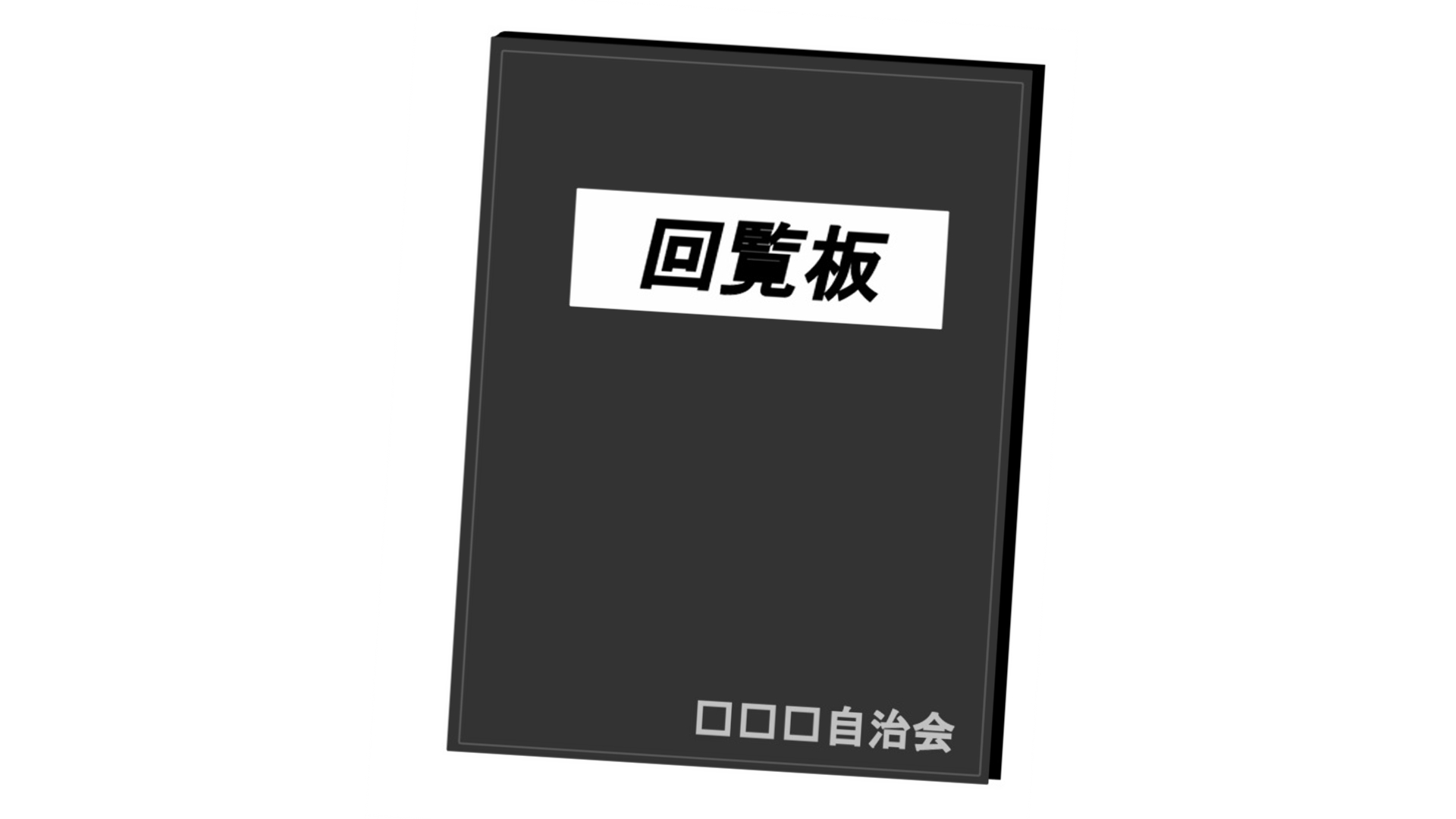町内会で長年続いてきた「回覧板」。
紙に印刷したお知らせを各家庭に順番に回す方法は、顔の見える地域コミュニケーションの一助となってきました。
しかし生活スタイルが変化した現代では、紙の回覧板だけでは対応しにくい場面がいくつかあると感じます。
今回は町内会の回覧板システムをより簡単で効率的にするための改善案をまとめていきます!
手回しの回覧板の課題

町内会や自治会で長年使われてきた手回しの回覧板には、便利な面もありますがいくつかの課題があり、「時代に合ってない」「古いやり方はもう限界」という声もチラホラあがります。
配布・回収に時間がかかる
紙を各家庭に手渡しで回すため、回覧が完了するまでに日数がかかります。特に忙しい家庭や不在が多い家庭があると、情報が届くのが遅れてしまうことがあります。
役員や班長の負担が大きい
回覧板の管理や配布、回収の確認は主に役員や班長が担います。日中に家にいないような忙しい人にも役割が回ってくるため負担の大きさが問題となります。
情報の見落としや紛失
回覧板が途中で置き忘れられたり、家庭内で見落とされたりすると、重要な情報が届かない可能性があります。
更新や追加情報の対応が困難
後から追加で知らせたい情報が出ても、すでに回覧が始まっている紙には追記ができません。再配布する必要があり、二度手間になります。
いつでもどこでも読めない
紙の回覧板は手元にないと読めません。そのため、次の家に回してしまうと読み返すことはできません。
また、紙を受け取っても常に持ち歩けるわけではないため、外出中などには内容を確認できず、必要な情報をすぐに見返せないことがあります。
回覧板をなくすことは可能?
「そもそも回覧板をなくしてしまえば、こんなことで悩まなくて良いのでは?」そう思うかもしれませんね。
現在、回覧板で伝達している情報はこのような内容が中心です。
- 行事の案内(盆踊り・清掃・集会・講演会など)
- 防災・防犯に関する通知(避難訓練・不審者情報など)
- 自治体や行政からの連絡(ゴミ出しルール・予防接種の案内など)
- 募金・集金のお願い
時々行政のルール変更でゴミ出し方法が変わることもあります。
「スプレー缶の穴あけが不要になりました。個人の穴あけで全国で事故が多発していることへの防止処置です。次の回収からは穴を開けずに使い切ってから出して下さい」という情報があれば、かなり重要なお知らせですよね。
町内会の情報伝達には一定の意味があり、完全になくすということはできないように思えます。
2つの改善アプローチ

すでにある紙の回覧板を工夫し改善しながら、さらにデジタルツールを導入することで、情報伝達をより効率的にする方法を紹介します。
①紙の回覧板を工夫する
- 必要な情報のみに絞って、内容・頻度を減らす
- 班に1つではなく複数送ることで伝達速度を早める
文字がたくさん書き込まれた内容だと読むのが面倒ですし、必要ない情報まで書かれると読み手の心理としては「もう読まなくてもいいかな」という気持ちになってしまい、重要な情報までも読まなくなってしまうおそれがあります。
そのため情報は絞って必要最低限で伝えるべきです。
また、1班に1つの回覧板ではなく、複数同時に配ることで1週間以上かかってやっと戻って来るものが2~3日に短縮できるようになります。
家が近ければという条件つきではありますが、「班長→Aさん→Bさん→班長」といったように、少ない人数で回すほうが早く伝達できてすぐに班長に戻って来るようにできます。
②デジタルツールを活用する
- LINEグループ・オープンチャット
- メール
- Googleドライブ・共有フォルダ
- ブログ・note
- 町内会アプリ
今はいろんな手段があって好みのものを選ぶことができます。デジタルに慣れた人が中心であればこうした選択肢もありです。
デジタル版のメリット・デメリット
回覧板をデジタルにするとこんなメリットがあります。
政府のサイトのURLを貼るだけなら、自分たちで詳しい説明を考える必要がなく、手間を減らせます。
簡単な内容が分かるタイトルを付けて、「詳しくはこちらをご覧ください」と伝えるだけで済みます。
しかしデジタルにはデメリットもあるので十分な話し合いが必要です。
ご年配の方など、デジタル端末に慣れていない方が多いと、「みんな使いこなせるのだろうか」「覚えるのが大変そう」と不安に思うこともあります。
しかし一方で、若者世代にとってはデジタルのほうが圧倒的に便利です。手作業やFAX、紙での手渡しといった古いやり方に手間や面倒を感じ、場合によっては嫌気がさす人も少なくありません。
今の若者は、電話ですら面倒だ・苦痛だ・時間を取られるのが嫌だと感じる人が多いです。
理想はハイブリッド型
個人的に理想だと思うのが、紙とデジタルのハイブリッド型です。紙の回覧板も残しつつ、デジタルに少しずつ移行していき、おのおの好きなスタイルを選択できるのがいいかと思います。
- デジタルに自信のない人は紙版
- スマホを持っていない人は紙版
- 回すのが面倒だと思う人はデジタル版
- 家に不在のことが多い人はデジタル版
紙には紙の、デジタルにはデジタルの良さがあります。どちらが便利と感じるかは人それぞれなので、選択できるように両方あるのが理想だと思います。
デジタルツールを選ぶときに大切なポイント
デジタルツールにはいくつか種類があってそれぞれに得意不得意なことがあります。以下の点に注目しながら選ぶことで、利便性を感じて自然と継続できる仕組みに繋がっていきます。
- 使いやすさ
→誰でも簡単に使いこなせるか - 更新・運営のしやすさ
→投稿や管理が簡単にできるか - スマホに通知がくるかどうか
→重要なお知らせが流れて埋もれない仕組みがあるか - セキュリティ・プライバシー
→個人情報が漏れない仕組みになっているか - 過去情報の見やすさ
→以前の回覧情報を簡単に引き出して確認できるか
次の人に引き継ぎできることが大切
多くの自治会ホームページが更新されずに放置されているように、後々のことをあまり考えずに始めると仕組みの継続が難しくなることがあります。
大事なのは「誰でも更新できる仕組み」を整えることです。
- 難しいシステムを選ばない
- 簡単で習慣化しやすい仕組みを選ぶ
- 更新担当を複数人にして「特定の1人しかできない」を防ぐ
ホームページの作成や更新は、町内会でどれだけの人が使いこなせるでしょうか。見ることはできても、作ったり更新したりするのは誰にでも簡単にできることではありません。
そのため、立ち上げた人以外にもスムーズに引き継げる仕組みを選ぶことが大切です。
デジタルツールのそれぞれの特徴
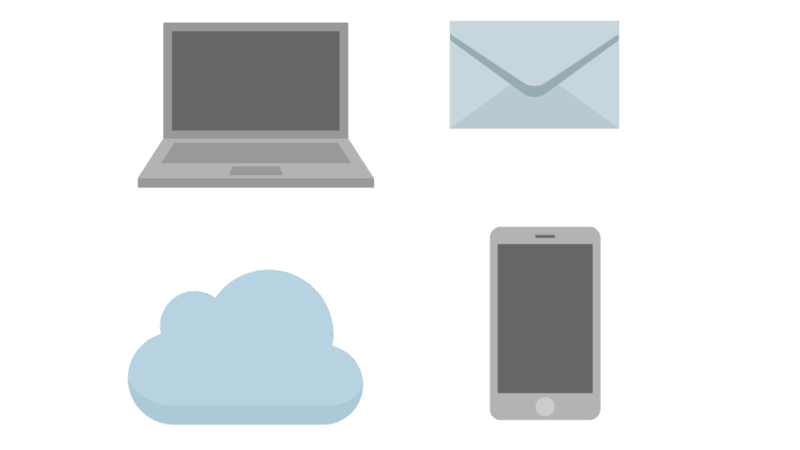
代表的なデジタルツールの特徴と、回覧板として選ぶ際のポイントを整理します。
LINEグループ・オープンチャット
メッセンジャーアプリ「 LINE (ライン) 」はすでに使っている人が多いので導入しやすいのが特徴です。
| 利用者の利便性 | 運営の利便性 | 通知性 | プライバシー | 見返しやすさ |
POINT
すぐに読んでもらいたい内容や簡単な情報共有に向いています。
メール
メールは情報を履歴として残しやすいのが特徴です。
| 利用者の利便性 | 運営の利便性 | 通知性 | プライバシー | 見返しやすさ |
POINT
昔からある仕組みなので馴染みがある人が多く導入が簡単です。
ブログ・note
ブログやnote(ノート)は多くの人に見てもらうのに向いています。
note とは?
誰でも簡単に記事や文章を公開できるウェブ上の発信プラットフォームです。文章だけでなく、画像や音声、PDFなども載せられ、幅広い情報を届けられます。
| 利用者の利便性 | 運営の利便性 | 通知性 | プライバシー | 見返しやすさ |
POINT
公共性の高い情報を発信したい場合に向いています。非会員の割合が多い地域でも有効です。
Google Workspace
「Google Workspace」 (グーグル ワークスペース)とは、Googleが提供している複数のWebサービスをまとめた総称です。
代表的なものは次のとおりです。
- Gmail(メール)
- Googleドライブ(ファイル保存・共有)
- Googleカレンダー(予定管理)
- Googleフォーム(アンケート作成・集計)
- Googleチャット(会話ツール)
- Googleドキュメント(文書作成)
このほかにも便利なサービスがたくさん含まれています。
基本的な機能は無料で使えますが、容量や管理機能を強化した有料のアップグレード版も用意されています。
たとえばGoogleドライブ を使えば、Word・Excel・PowerPointで作成した資料をクラウド上に保管し、町内会メンバー全員がいつでもどこからでも閲覧できます。
Googleフォーム を使えば、町内会のアンケートを簡単に作成でき、回答の回収や集計も自動で行えるため、手間を大幅に減らせます。
| 利用者の利便性 | 運営の利便性 | 通知性 | プライバシー | 見返しやすさ |
POINT
Google Workspaceだけでなく、Microsoftからも「Microsoft 365」という同様のWebサービスが出ています。
自治会・町内会向けアプリ
今は自治会・町内会向けにアプリの提供も進化しています。
| 利用者の利便性 | 運営の利便性 | 通知性 | プライバシー | 見返しやすさ |
POINT
PCを持っていない人でも簡単に使えるうえ、多機能が1本にまとまっているので利用者には非常に便利です。通知の送信・アンケート集計・読んだ人の把握など自動でできることも多く、運営側の負担も少なくなります。
若者を取り込んで町内会に新陳代謝を!
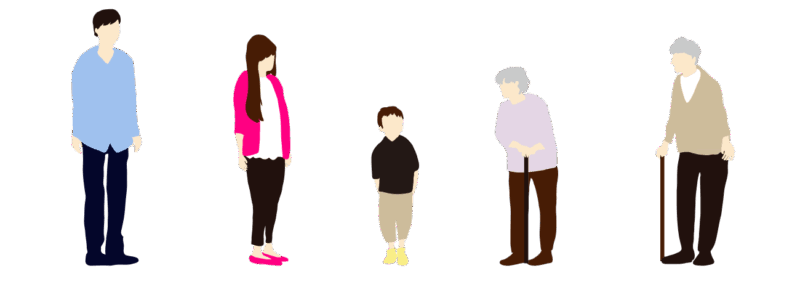
デジタルと紙を両方運用するのは運営側にとって手間がかかるかもしれませんが、若者世代にとってはアンケートや出欠連絡がデジタルでできる方が圧倒的に便利です。
そのため、デジタル化(DXとも言います)は若者を町内会に取り入れる手段としても有効です。紙よりデジタルの方が見やすく、効率的だと感じる若者は多く、若者と年配世代が共存する町内会の姿に希望や期待を持つことができます。
古い習慣にとらわれず新しい仕組みを取り入れる町内会の姿は、若者に「ここなら自分たちも未来を一緒に作れるかもしれない」と感じさせ、変化の大きなきっかけになるかもしれません。
任せてみるのもひとつの手
もし年配の自分たちでデジタルの導入が難しいと感じるのであれば、若者に任せてみるのも一つの方法です。
これまで年配者の顔色をうかがいながら控えめに過ごしてきた若者も、世代交代で活躍の場を与えられれば、意欲的に改革を進めてくれるかもしれません。
まとめ
- 内容を減らして頻度を減らす
- 紙とデジタルの両方で選択できる形にする
- ライフスタイルや好みに合った選択ができるとよい
紙の回覧板を工夫しつつ、デジタルツールを取り入れることで、世代間の溝をなくしながら情報伝達をスムーズにできます。
町内会から人が離れていく原因は、時代は変わったのに古いやり方を続けていることかもしれません。まずは常識を見直して、新しい一歩を考えてみませんか?
こちらの記事もおすすめです↓