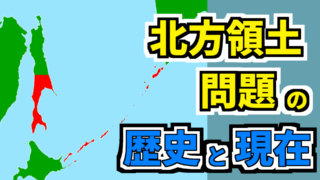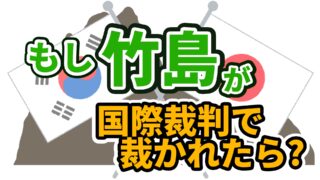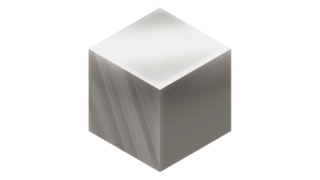町内会は昔から地域のつながりや生活のサポートにとても大事な役割を果たしてきました。
でも最近は「参加するのが大変」「本当に必要なの?」と感じる人も増えて加入率の低下が課題となっています。
では、どうして今の時代に町内会が合わなくなったのか、理由を見ていきましょう。
家族構成の変化
昔は大家族が当たり前で、家族の人数が多い分だけ知り合いの幅も自然に広がり、地域とのつながりも強くなるものでした。
祖父母・親・子どものそれぞれが知人を持ち、家庭内でそれを話し合うことで自分と直接かかわりがなくても自然と知り合いが増えていきました。
一つの家庭の中で複数の世代とつながることができたため、それぞれの世代ごとの困り事も “自分たち家族に関わる問題・課題” となり地域全体でも助け合いが生まれやすくなりました。
ところが現代では夫婦だけや単身世帯といった少人数の世帯が増えて、地域との接点が少ないのが普通になりました。
地域の人と仲良くしようとする、従来のようなつながりの強さは薄れてきています。
生活スタイルが多様化
昔は多くの家庭で専業主婦世帯が一般的でした。そのため、町内会活動に参加する人手が十分にありました。
朝のゴミ出しの見張りや、地域行事の準備、掲示板の管理などの町内会活動やに自然に参加できる環境が整っていました。
現代では共働き世帯や単身世帯が増加し、家庭の生活リズムが多様化しています。早朝から仕事に出かけたり夜勤で働くスタイルもあり、町内会の活動時間と合わないことが増えました。
- 朝6:00~8:30の間ゴミステーションの見張りをする
- 朝のゴミ回収が終わった後ネットを片付ける
- 土日は行事の計画・準備・運用
その時間に仕事で離れていたらこれらは参加できませんよね。
結果として、町内会活動に必要な人手が不足し、従来のペースで活動を進めることが難しくなっています。また、参加できる人の負担が偏ることもあり、不平不満が出てきている状況です。
住む人が入れ替わりやすい
昔は一度その土地に住み始めると、長く暮らすのが当たり前でした。
- 持ち家率が高く、親から子へ家や土地を受け継ぐことが多かった
- 仕事も地元で見つける人が多く、転勤は今ほど多くなかった
- ご近所同士の顔ぶれがほとんど変わらず、世代を超えて知り合い同士だった
そのため、町内会も「長年一緒に暮らしてきた人同士で支え合う仕組み」として自然に機能していました。
ところが今は状況が大きく変わっています。
- 転勤や就職、進学に合わせて数年単位で引っ越すのが一般的
- 賃貸住宅や新興住宅地では短期間で入居者が入れ替わる
- 地域に長く根を下ろす人が減り、近所付き合いが長続きしにくい
こうして住む人の顔ぶれが頻繁に入れ替わる現代では、町内会が昔のように「地域の安定したつながり」を前提に成り立つことが難しくなっています。
行政や業者がやってくれることが増えた
昔は行政サービスが今ほど充実していなかったため、生活に必要な多くのことを町内の住人が協力して担っていました。
- ゴミは庭や空き地で燃やす
- 不用品は近所の人に譲る
- 防犯の見回り
- 冠婚葬祭の手伝い
昔はこれらを地域住民が行うのが当たり前でした。
でも今は行政や専門業者のサービスが大幅に充実し、町内会に頼らなくても生活が成り立つようになっています。
趣味や価値観が多様化
昔は、地域の人々が似たような趣味や価値観を共有していました。
娯楽といえばテレビやラジオ、釣りや盆栽など選択肢が限られており、「いい学校に行き、安定した職に就き、結婚して家庭を持つ」というのが多くの人にとって共通の目標でした。
「夜は家でテレビを見る」「休日は近所で過ごす」といった具合に、みんなが似たような生活リズムを送っていた時代では、地域行事のため同じ時間に集まるということも、ごく自然な流れだったのです。
ところが今は、インターネットやSNSを通じて多様な情報や人とつながれるようになり、趣味や価値観は細かく分かれるようになりました。「自分らしく生きる」「自分の時間を大切にしたい」という人も増え、必ずしも地域とのつながりを強く求めない人が多くなっています。
このように生活スタイルや価値観が多様化する中で、「みんなで同じことを一緒にやる」ことを前提とした町内会の活動は、以前ほど自然には受け入れられなくなってきています。
まとめ
もともと町内会はその時代の人々の生活に必要な仕組みであり、支える人もいたからこそ成り立っていました。
しかし今は行政サービスや代行業者が充実し、生活スタイルや価値観も多様化しています。その中で、顔も知らない地域住民のために働くことに意味を見いだせない人が増えているのが現実です。
- 回覧板 : 夜遅く帰宅する人も多く、短期間で回すのは難しい
- 班長や役員 : 仕事で忙しいのに「順番だから」と役割が回ってくる
- 募金活動 : 何のためか分からないまま強制的に徴収される
- 行事不参加の罰金 : 仕事や育児で参加できない人にとって理不尽
- 地域の祭り:「絶やしたくない」「子どもたちのため」で続けているが運営の負担は大きい
現代に合わせて必要性に応じたかたちで、町内会は再構築するとよいのではないでしょうか。
どう変えるかは地域の特色や事情によります。ですが少なくとも、次の点は住民同士で話し合って決めるべきだと感じます。
みんなが納得できる形を探ることで、町内会は今の時代にも合った、心地よいつながりの場として生まれ変わっていけるのではないでしょうか。