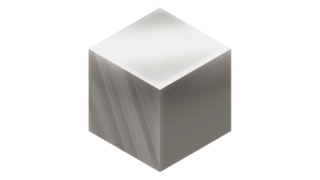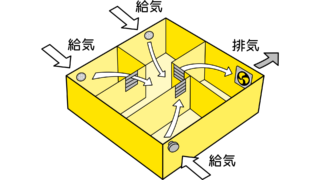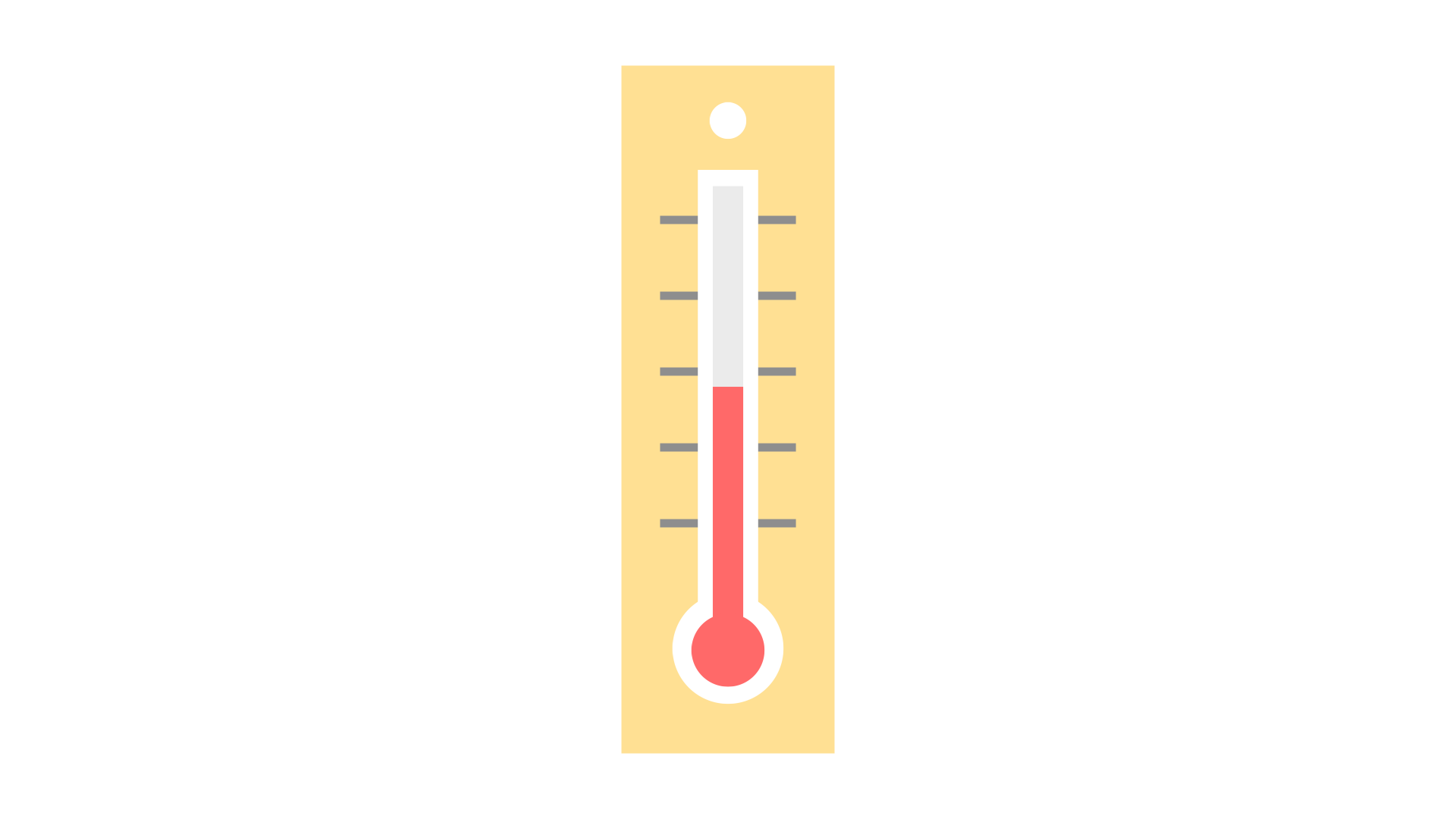今回は摂氏と華氏の違いについて気になるので調べてみました。摂氏は私たち慣れていて分かってますけど、華氏ってよく考えると色々と謎が多いですよね。
摂氏と華氏の違い
摂氏(℃)は水の変化を基準にしていて、水の凍る温度が0℃で沸騰する時の温度が100℃なのは皆さんご存知ですよね。
じゃあ華氏(°F)は何なのよ?!というと、「塩水が凍る温度を0°Fと定めて作られたもの」になります。
華氏は、18世紀初頭にドイツの物理学者ガブリエル・ファーレンハイト(Gabriel Fahrenheit)が考案した温度の表示方法です。
現在でもアメリカでは主流の単位として使われていますが、アメリカ以外の国ではあまり一般的ではありません。(ただし、アメリカに近いカナダやバハマなどでは、摂氏と華氏が併記されたり、場面に応じて使い分けられることもあります。)
その他の国では基本的に摂氏が使われています。理由はとてもシンプルで、摂氏の方が直感的で分かりやすいからです。
水が凍る温度を0℃、沸騰する温度を100℃として、その間を100等分する仕組みなので、化学の授業などで学ぶときにもスムーズに理解できるのです。
イギリス・オーストラリア・ニュージーランド・インドなど、かつては華氏だったのが「摂氏の方が分かりやすくて便利じゃん」ということで移行した国もあります。
ファーレンハイトの実験内容
物理学者ファーレンハイトは、塩を加えた氷水の温度が安定する点を探しました。
塩水に氷を入れると最初は水の温度が下がりますが、やがてどれだけ氷を入れても温度がほとんど下がらず安定していきます。
そして最終的には氷が溶ける力と水を冷やす力が釣り合い、これ以上氷は溶けない・水もそれ以上冷えない状態になります(融解平衡)。これが0°Fです。
なぜ氷水を使ったの?
ファーレンハイトが実験を行った1700年代は、実験のために用意する水の純度や器具の精度が現代ほど高かったわけではありませんでした。
そのため、より実験の再現度が高く、結果が安定して得られる塩水が採用されました。
塩を入れると水が凍る時の温度が下がります。こうして融点を下げると次のような違いが生まれます。
純水の場合
- 融点が高いため、融解平衡が早く訪れる
- 少ない氷で終わる
- 融解平衡が終わり、氷が溶け始めるまでの時間が短い
塩水の場合
- 融点が低いため、融解平衡に時間がかかる
- 大量に氷を使う
- 融解平衡が終わり、氷が溶け始めるまでの時間が長い
塩水のほうが「しばらく同じ温度を保つ状態」が続き、測定に余裕が生まれます。また、より多くの氷を使って冷やすことになるので実験環境が安定的になります。
氷と塩を一定の比率で混ぜるだけで同じような温度を何度でも作れて、研究者仲間が実験を再現しやすい点も大きなメリットでした。
さらに、当時は「低い温度をはかるための基準」がまだなく、「氷点下の世界」つまりマイナスの温度を表すことができませんでした。
そこで役に立ったのが「塩を混ぜた氷水」です。塩を加えることで、純水の氷よりも低い温度を安定して作り出すことができ、そのおかげで「マイナスの温度を正しく測るための基準点」として利用できたのです。
もう一つの温度基準
ファーレンハイトはその後、人間の体温がいつもほぼ一定であることに注目して体温をもうひとつの基準点にしました。
塩氷水に温度計を入れて示す液の高さと、体温を測った時の温度計の液の高さをもとに、2点間を細かく96等分にして目盛りをつけます。
こうすることで、純水の凍る温度は32°F、沸騰温度は212°Fとして表すことができ、計測に便利な温度目盛りが完成しました。
※記録が少ないため経緯は正確には分かっていません。諸説あるうちのひとつです。
それから体温を基準にしたのは、「身近にあって誰にでも分かる温度の基準だから」のようです。
長さの単位である「尺」も人によってバラバラなはずの手の大きさを基準にして作られました。長さの単位「フィート」も成人男性の足の長さが基準です。重さの単位「ポンド」は成人1人が1日で食べる大麦の量の重さが基準ですし、ダイヤの重さの単位「カラット」は豆1粒の重さを基準に定められました。
このように「身近なものを基準にすればみんなに分かりやすく伝わる」という理由で、正確ではない数字をもとに単位が作られることは珍しくありません。
それにしても分かりづらい華氏
それにしても水が凍るのが32°Fで沸騰温度が212°Fというのは、明日になったら忘れそうなくらい覚えにくいですし、体温までの温度を96等分したのもよく分かりませんね。
「°F」の読み方は「華氏◯度」や「◯度エフ」と読んだりするのですが、正式には「ファーレンハイト」と読むらしいです。100°Fは100ファーレンハイトと読みます。
摂氏であれば雪が降ったり池が凍ったりすると「ああ0℃なんだな」と境界線として分かりやすいですけど、華氏だと「ああ32°Fなんだな」というのは半端な感じがしてしっくり来ない感じがします。
摂氏と華氏の漢字の由来
意外と疑問に思われずにみんなからスルーされているのが「摂氏と華氏の漢字って何?どういう意味?」というところ。
摂氏:考案者のセルシウスの中国音訳「摂爾思(シェアルス)」の頭文字で摂氏
華氏:考案者のファーレンハイトの中国音訳「華倫海(ファーレンハイ)」の頭文字で華氏
こんな感じになっています。
なぜこんなにも分かりにくいのか?!その理由は・・・
どうしてこんなに分かりにくい温度基準を作ったのでしょうか。
ファーレンハイトは「自分や仲間の学者が使うのに便利な温度計を作りたかった」ただそれだけでした。
後世に一般的に使われる温度基準を作るつもりはありませんでした。自分が理解できて、便利であればそれで良かったのです。
体温を基準にして割った96という数字も、計算しやすく、2や3で割れる便利な数字だったからです。細かすぎず、大雑把すぎない、ちょうどよい大きさの数字として採用されました。
1度の幅が小さいほうが便利
ファーレンハイトは自分の実験ために温度基準を作りました。
1°F=0.556℃
1度の幅が小さいほうが細かく実験の仮説検証ができるため、便利だったと考えられます。
96°F→98.6°Fに変更された人間の体温
人間の体温は96°Fであると一度ファーレンハイトによって定義されたのですが、これが測定技術の進歩によって間違っている可能性がのちに指摘されます。正確には98.6°Fが人間の体温ということで19世紀中頃に訂正されました。
もともと人間の体温を基準に作られた華氏温度でしたが、基準の軸が変わったとしてもそれをもとに1°Fの大きさを修正することはありませんでした。その理由としては華氏の温度表記はこの時すでに広く使われていて、そこから変更してしまうとコストが膨大だったり混乱させてしまうからです。
さらに変更されなかった理由はもうひとつ。純水が凍る温度32°Fと水が沸騰する温度212°Fには変化がなかったというところです。
人間の体温の測定方法がファーレンハイトの時代ではそもそも正確ではなかったのでズレがあっただけで、水の融点沸点に関する実験には正確性があったのでそこは変化がありませんでした。
アメリカが華氏を使い続ける理由とは
現在も華氏を使い続けるアメリカですが、かつては華氏から摂氏に移行しようとした時期がありました。でも華氏を残したい派の反対によって今もなお残っています。
理由は「華氏に慣れ親しんでいるので摂氏表示になるとわけが分からなくなるから」だそうです。
たとえば「日本もこれからは華氏にしよう!」となったら私たち反対しますよね。それと同じです。
でもそんなアメリカでも化学を勉強する時には摂氏を使います。国際基準でそう定められているからとのこと。
華氏が使われる場面は、主に天気予報や日常会話で気温を表すときです。
たとえば「今日は最高気温が95°Fらしいよ」「プールの水温は80°Fだって、ちょうどいいね」「今日は25°Fだよ、寒いね」といった具合に使われます。
ただし、アメリカ人が摂氏と華氏を自由に頭の中で変換しているわけではありません。日常生活では気温を華氏で、科学的な説明や授業では摂氏で、といったように用途ごとに切り分けて使い分けているのです。
また、華氏を支持する人の立場からすると、日常会話で気温がマイナスになるのは不自然だと考えられています。
華氏なら気温をおおよそ20°F~130°Fの範囲で表せるので、常に正の数で示すことができて、直感的で理解しやすいらしいです。
さいごに
「文化の違い」と一言で片付けてしまえるものであっても、疑問を持って解消しておきたいと思う気持ちは大事だなと思います。「当たり前だから考える必要もない」と考えることをやめてしまわないようにして生きていきたいですね。
ところで、水が凍る温度と沸騰する温度は華氏でいうと何°Fと何°Fでしょうか? さっき見たばかりですが覚えていますか?