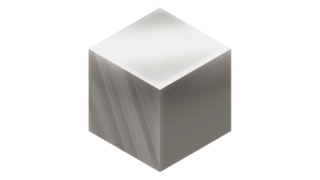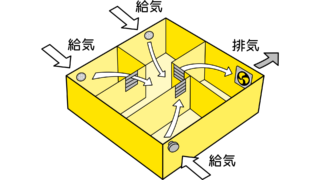今回は私の家でDIY設置した太陽光パネルの発電量の数値を見てみなさんと共有したいと思います。これから設置したいと考えている方の参考になれば幸いです。
どうして400Wにしたのか
| 100Wパネル | 400Wパネル |
|---|---|
| 価格 約8千円 | 価格 約3万円 |
| 使用用途 携帯電話の充電 | 使用用途 電子レンジ・炊飯器など |
| 災害時のみ活用 | 日常生活で活用可能 |
太陽光パネルを選ぶ際にまず最初に見るのがワット数ですね。
私の家には2種類の太陽光パネルがあって、最初に買ったのが100Wの折りたたみ式のもので次に400Wの屋外用パネルを購入しました。
100Wあればスマホなどバッテリー類の充電をするくらいなら十分なので最初は満足していたのですけど、「災害時に電子レンジ・電気ケトル・炊飯器を使いたい」と考え始めて大きめのポータブル電源を購入したのをきっかけに400Wの太陽光パネルを導入することにしました。
400Wは1枚200Wのパネルを2枚つなげて400W出力を出す仕組みです。パネルをどんどん増やせば単純に足し算されて出力が増えていきます。たとえば200Wが10枚あったら2000W(2kW)になります。
ただし家庭でDIY設置するにはスペースの限界がありますから沢山の数を置くのは大変だと思います。私は後々のメンテナンスのことを考えて屋根上ではなく2階バルコニーに設置したかったのでサイズ的に400Wを選択しました。
また、太陽光パネルをDIY設置する初心者の方にオススメなのがポータブル電源を使ったシステムです。ポータブル電源は面倒な配線や難しい知識を必要とせず誰でも簡単に導入できるのが最大のメリットです。詳しくは別記事で書いていますのでそちらも良かったらご覧ください。
正直なところ、手持ちのポータブル電源の容量的には200Wあれば晴れた日でギリギリ足りるくらいなのですが、①少々雲がかっても発電できる力が欲しい②後で増設するより最初から2枚で作る方が作業が楽③スペース的にも全然入る④2枚セットがお買い得だった、という理由で400Wにしました。
400Wパネルの実際の発電量
さて気になる実際の発電量ですが、まだ導入から1年経っていなくて季節が冬~春と限定的ではありますが次のようになっています。
天候が晴れの場合
| AM 7:00 | 50W |
| AM 8:00 | 120W |
| AM 9:00 | 200W |
| AM 10:00 | 300W |
| AM 11:00 | 380W |
| PM 0:00 | 360W |
| PM 1:00 | 270W |
| PM 2:00 | 200W |
| PM 3:00 | 150W |
| PM 4:00 | 100W |
| PM 5:00 | 20W |
| PM 6:00 | 5W |
太陽が雲にかかっていない晴れの日は11時~12時頃のピーク時に400Wに近い数字が出ます。上の表は偶然の好条件の日というわけではなく、晴れれば毎日出るような基本的な数字です。後で詳しく書きますが条件が整った日は最高で422Wまで叩き出してくれました。
夕方はまだ太陽が出ていてもあまり発電できません。冬の17時台は全然明るいのですが、太陽の角度が斜めになると発電力がかなり落ちるらしく、20~40Wくらいになってしまいます。朝と夕方は角度が低いことに加えて、光が大気の中を長く通過してから地表に届くため光が減衰して発電量がガクッと落ちます。
天候が曇りの場合
| AM 7:00 | 5W |
| AM 8:00 | 10W |
| AM 9:00 | 25W |
| AM 10:00 | 40W |
| AM 11:00 | 60W |
| PM 0:00 | 50W |
| PM 1:00 | 35W |
| PM 2:00 | 20W |
| PM 3:00 | 15W |
| PM 4:00 | 5W |
| PM 5:00 | 0W |
| PM 6:00 | 0W |
曇りと一言で言っても曇り具合が様々なので伝えるのが難しいですけど、この場合は空全体が雲で覆われていて太陽の場所がかろうじて分かるくらいの天気です。降水確率で言うと30%くらいでポツポツ雨なら降ってもおかしくないけど傘は要らない、そんな天気です。
晴れの日と比べるとかなり少なく感じますね。雲がかかると太陽の光がかなり遮られる(拡散する)ようで、発電量はガクッと落ちます。なので晴れの日がどのくらいあるかという地域による差が結構重要だと感じます。あと、晴れた日でも太陽が雲に隠れた時は一時的に上のような数字にもなります。
それから太陽を遮る雲が一見無いように見えても、空気中の水蒸気量が多ければパネルまで届く光が減って発電量が下がることもあります。パネルの発電量が思ったほど出ないという場合は、パネルの製品不良の可能性もありますが天候条件が良くないということも十分考えられるのでご注意ください。
太陽光パネル購入直後の私の話ですが、最初晴れた日に測定したのにピーク時で150Wしか出なくて「不良品なのかな?!」と思ってかなり焦った経験をしました。でも晴れたように見えても空気中に肉眼では見えない薄い雲があったり水蒸気量が多かったりすると空中で光が拡散してパネルまで届きにくいということもあるようです。パネルの初期不良は1日や2日程度では判断できませんのでご注意を。
天候が雨の場合
| AM 7:00 | 0W |
| AM 8:00 | 0W |
| AM 9:00 | 2W |
| AM 10:00 | 5W |
| AM 11:00 | 15W |
| PM 0:00 | 12W |
| PM 1:00 | 5W |
| PM 2:00 | 5W |
| PM 3:00 | 2W |
| PM 4:00 | 0W |
| PM 5:00 | 0W |
| PM 6:00 | 0W |
雨の日は発電はもう諦めてください。普通にコンセントからの電気を使いましょう。
というわけで明日の天気を見て雨の場合はポータブル電源を使い切らないようにするといった調節が必要になります。
まあそれでも携帯の充電をするくらいの発電量なら確保できますね。停電の非常時に雨の日でもスマホが使えるのであれば、まあいいのかもしれません。
今回のパネルの設置条件
先に結論の方から知りたいかなと思って細かい設置条件を後回しにしましたが、今回の私の家での設置条件はザックリこんな感じになっています。
- 200W+200W=400W出力
- 直列つなぎ
- 単結晶シリコンパネル
- 最大変換効率21%(製品性能表より)
- パネルの向きは南南東
- 影ができる部分は無し
- 長さ10mのケーブルで配線
- パネル角度は約60度
- 観測時の季節は冬~春
- 場所は本州太平洋側で住宅地
200W2枚を直列つなぎ
ポータブル電源の能力的に大丈夫だったので200Wパネル2枚を直列で繋いでいます。
ポータブル電源が小さくて性能が高くない場合や、違う種類のパネルを組み合わせる場合は電圧を下げたり一定にするために並列つなぎを採用することもあります。
パネルの向きは南南東
パネルの向きは家の角度との兼ね合いで南南東を向いています。なので発電のピークが正午よりも少し早めに来るようです。
長さ10mのケーブルで配線
2階のバルコニーに置いた太陽光パネルから、日常的に使える1階に配線したので10mという割と長いケーブルで繋いでいます。なのでパネルで発電した電気量よりも少しロスが生じたうえでポータブル電源に入って表示されています。
ちなみに1階室内へはエアコンの排気口のために空いた壁の穴からケーブルを入れました。途中で断熱材が邪魔してきますが、金属製の棒にケーブルをテープで貼って棒を押し込めば貫通させることができます。
パネル角度は約60度
パネル角度は最適ではない60度です。日本の緯度は24度(沖縄)~45度(北海道)なので緯度に合わせた角度でパネルを設置するのがベストです。たとえば東京の場合は緯度35度なのでパネルの角度は35度で設置するのが基本です。
あとは季節によって変わる太陽の角度に合わせてパネル角度も変えるとさらに効率が上がります。
私の場合はバルコニーにあまり奥行きがないため急角度でしか設置できませんでした。
ちなみにパネルと壁には隙間がないといけないのでご注意ください。
- 熱を逃がすため
- 雨水を溜めないため
- 影が入らないようにするため
といった理由からです。
場所は本州太平洋側で住宅地
場所は本州の南側で、北側と比べると晴れの日が多い地域のようです。高い山が近くにない住宅地なので雲が停滞することも少ないかもしれません。
観測時の季節は冬~春
今回の記録の観測時期は冬~春です。比較的寒い日の観測なので理論値に近い高出力が可能になったと考えられます。次の項目でその理由を見ていきましょう。
400Wに近い数字が出たのはなぜ?
今回夏ではなく冬から春にかけての寒い時期の観測ということで、ピーク時に400Wに近い数字で毎日発電できているのですが、それにはこんな理由があるようです。
太陽光パネルの定格出力を決める条件
太陽光パネルの定格出力は以下の条件で測定試験を行って決定されています。
標準試験条件(STC)
- 光照射強度 : 1000W/m²
- 温度:25°C
- スペクトル : AM1.5
この温度25℃の部分についてですが、これは観測試験する時のパネルの温度を25℃にした時のものです。これよりも高い温度になると1℃の上昇ごとに発電効率が0.5%ずつ下がると一般的に言われています。
なぜ25℃なのか?
25℃という値は一定の基準を設けるために設定された数字に過ぎません。特にこの25℃がパネルの最大効率を出せる温度というわけではないようです。太陽光パネルの種類もいろいろあるわけですよね。
- 単結晶シリコン
- 多結晶シリコン
- アモルファスシリコン
- CIGS
- CdTe
- ペロブスカイト
最適な温度がそれぞれで違うので25℃を何かの境界線にしているわけではありません。
そしてシリコンパネルの場合、25℃よりも低い温度の場合は発電効率が上がることが分かっています。
| 26℃以上 | 効率ダウン |
| 25℃ | 基準値 |
| 15℃~24℃ | 効率アップ |
| 14℃以下 | 効率ダウン |
低温で効率が上がるのはなぜ?
シリコン素材の特性で温度が低いと内部抵抗が減少して電力変換効率が向上するため、低い気温の冬の方が内部的には効率の良い状態になります。
ただし冬は太陽が空に昇っている昼の時間が短いので他の季節よりも発電量は低くなります。積雪地帯の場合はパネルに雪が積もって発電がほぼできない状態にもなるので、それも冬に効率が下がる一因となっています。
また14℃以下で発電効率が下がるというのもシリコンの特性や絶縁体の性能低下が原因です。
逆に夏場は晴れが多くて日差しも強いので太陽発電にもってこいの季節かと思いきや、パネル温度が高温になるので効率が下がって思ったように発電できないことが多いようです。
今回は比較的寒い時期での観測だったので効率よくパネルが稼働してくれた結果、400Wに近い数字が出たと考えられます。好条件が整えば400Wを超えて420W出してくれることもあるので快晴の日は気分も晴れやかになります^^
また私の場合はスペースの関係でパネルの角度が60度の急角度になってしまったので、ベストな角度で設置できればさらに良い数値を叩き出すかもしれません。
年間の発電量はどのくらい?
この記事を書いている時点ではまだ導入から1年経過してないので実績値は出せないのですが、予測値なら出すことができるので見ていきたいと思います。
| 月 | 平均発電量(kWh/日) | 発電量の増減の理由 |
|---|---|---|
| 1月 | 1.2~1.6 kWh | 日照時間は短いが、晴れの日が多く、気温が低いため発電効率が高い。 |
| 2月 | 1.4~1.8 kWh | 徐々に日照時間が長くなり、冬晴れも続くため発電量は増加。 |
| 3月 | 1.6~2.2 kWh | 春分を迎え日照時間が増える。天気が安定している日も多い。 |
| 4月 | 1.8~2.4 kWh | 晴天率が高く、太陽高度も上がり、発電に適した時期。 |
| 5月 | 2.0~2.6 kWh | 1年の中で最も発電量が多い。晴れの日が多く、日照時間も長い。 |
| 6月 | 1.4~1.9 kWh | 梅雨入りし、曇りや雨の日が増えるため発電量が減少。 |
| 7月 | 1.6~2.1 kWh | 夏至で日照時間は長いが、梅雨明けまでは不安定。梅雨明け後は増加。 |
| 8月 | 1.8~2.3 kWh | 晴れの日が多く発電量は多いが、気温が高くなりすぎると効率が落ちる。 |
| 9月 | 1.6~2.1 kWh | 台風シーズンで曇りや雨の日が増え、発電量が不安定。 |
| 10月 | 1.8~2.3 kWh | 秋晴れが多く、気温も適度に下がるため発電量が安定。 |
| 11月 | 1.6~2.1 kWh | 日照時間が短くなり始めるが、晴天率が高いため発電量はそこそこ確保できる。 |
| 12月 | 1.3~1.7 kWh | 日照時間が最も短くなるが、冬晴れが多く発電効率は良い。 |
年間の発電総量は660kWhで1日あたりの平均が1.8kWhとなります。電気代にすると単価27円/kWhの場合で年間17820円、1日平均で約49円の節電になるようです。
ただしこれは発電した電気をフルで使えた場合の話です。実際にはそんなに電気を使えないというシーンもありますよね。
- 外出中に蓄電池が満タンになってしまった
- 家にいても満タンに気づかなかった
- 今すぐ消費できる電気がなかった
こういったことがあると日中の発電が無駄になってしまいます。フル活用して電気代節約を目指す場合は日々の計画性が重要になってきますね。
さいごに
400Wのパネルをつけてみた感想としては、「晴れた日はオーバーなくらい発電できる一方で、曇りの日と雨の日は極端に発電量が低いので運用が難しい」と感じます。
なので日常的に使いたいのであれば天候によって左右されにくいように、ポータブル電源を1日の使用量以上の大容量のものにするか複数持つかのどちらかでストックを用意することも大事ですね。
非常時の備えとして用意する場合も、その日が晴れとは限りませんし数日耐えられるような設計を目指していくのもアリだと思います。こうしてどんどん沼にハマっていく・・・(笑)